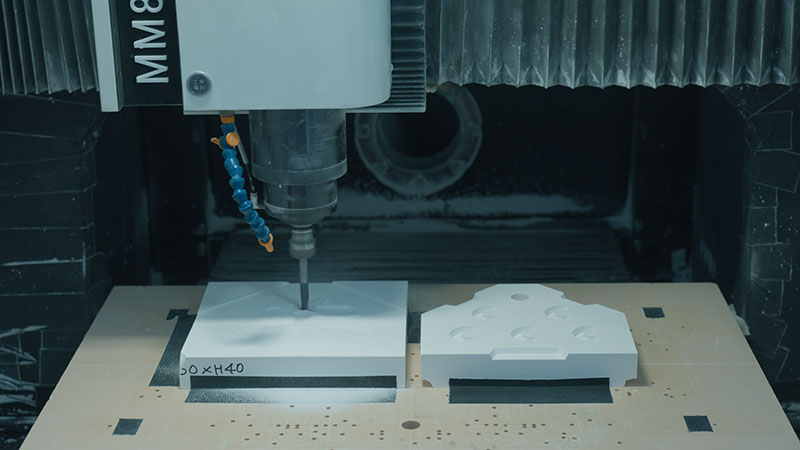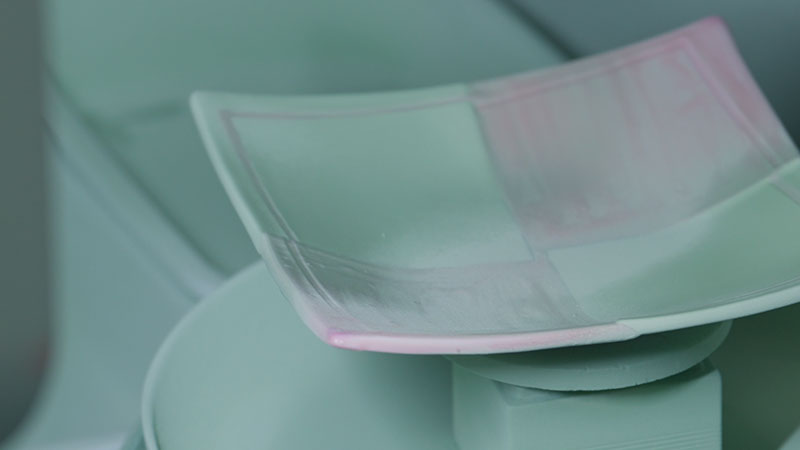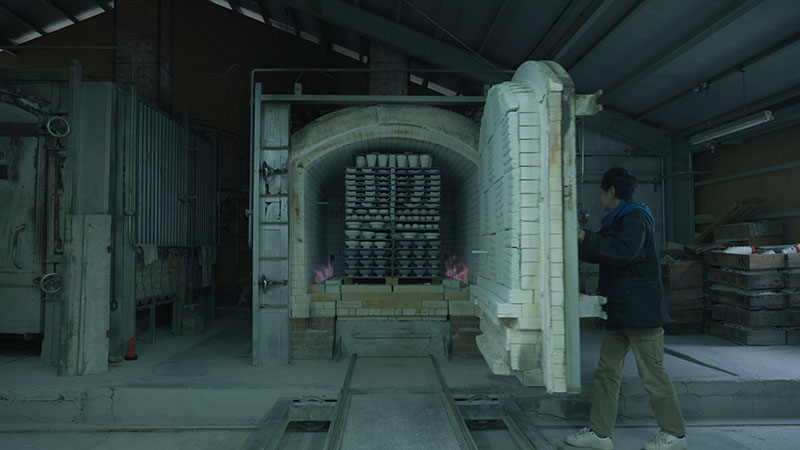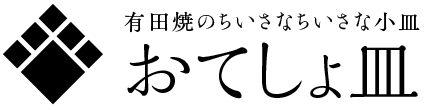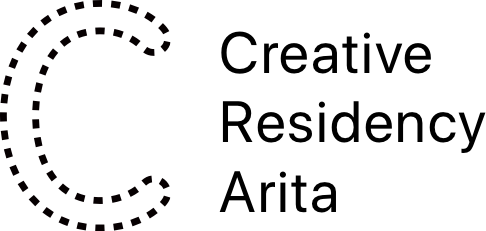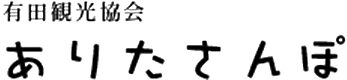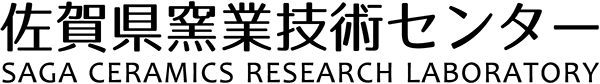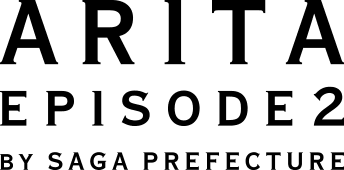有田焼についてAbout Arita

有田焼の歴史History of Arita
有田のやきものの歴史は、1600年代の陶器生産にはじまります。そして、1616年に有田に移り住んだ朝鮮人陶工金ヶ江三兵衛(通称:李参平)らによって日本磁器が開発され、1630年前後に良質で豊富な泉山陶石が発見されたことで本格的な産業的磁器生産体制が確立し、今日まで連綿と続く窯業の基盤が築かれました。
その後17世紀後半には、国内にとどまらず、オランダ東インド会社を通じて世界中に運ばれるようになり、世界の磁器生産の中核地としての地位を確立しました。
濁手と呼ばれる乳白色の素地に繊細な絵付けが印象的な柿右衛門様式、金彩をふんだんに用いた絢爛豪華な古伊万里様式など、その作品は「白き黄金(こがね)」とも形容され、欧州の王侯貴族などの間でももてはやされ、各地の宮殿を華やかに彩りました。
また、1640年代後半には有田の岩谷川内山で御道具山(藩窯)制度が確立し、1651年からは将軍家などへの例年献上もはじまりました。その技術をもとに、後に御道具山は伊万里の大川内へと移され、有田から各時期の優秀な陶工が集められ、格調高い鍋島様式が生産されました。
有田では、こうした伝統に根ざしたさまざまな技術や製品様式をベースとしつつも、各時代の要求を柔軟に取り入れ、今日でも常に新しい有田焼が生み出され続けています。